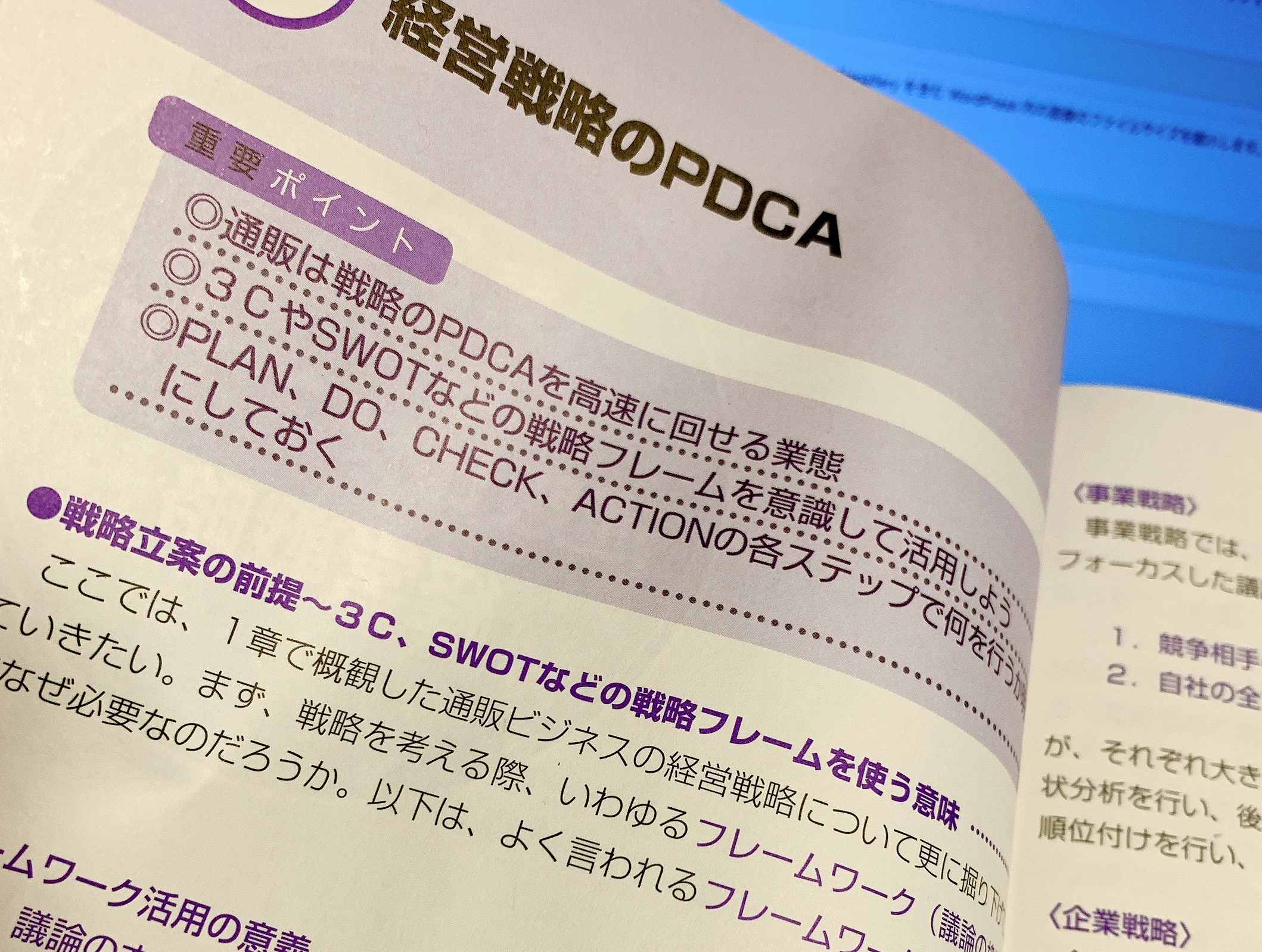「通販エキスパート検定1級」という一般財団法人通販エキスパート協会が主催している民間資格を受験してみました。
はじめに
普通、こういう資格を取るときは会社から援助があったり、「業務命令だ!受けてこないと減給だ!!」と言ってくれるとありがたいんだけど、一向に誰も助けてくれないので、自腹で受けてきました。
大好きな竹原ピストルの「虹を待つな、橋を架けろ」の精神で。
受験料は、たしか8,500円もした。だから、失敗は許されません。なのでちゃんと合格しました。
さて、この記事にたどり着いたあなたは、きっと通販エキスパート検定を受験しようとしているのだと思います。
- 何から勉強すれば良いの?勉強方法は?
- 勉強時間はどのぐらいで合格する?
- テキストや問題集は買わなくていいの?
- セミナーは受けた方が良い?
- 難易度はどのぐらい?
…などなど、疑問に思うこと、知っておきたいことがいくつもあると思います。私も、そうでした。みんな考えることは同じです。
その不安を解消しようと、受験体験者のブログでも拝見しようかな…。そんな行動をとりますわね。普通。
ところが、通販エキスパート検定がマニアックな資格なのか知らないけど、ググっても、該当記事があまり出てこないんですよ。2旧の記事は
そこで、これから通販エキスパート検定を受験しようとしている、まだ知らぬ仲間に、少しでも参考になれば…と思い、備忘録をここに残しておくことにしました。
通販エキスパート検定の基本的な情報は公式サイトをチェックしていただくとして、実際に受験→合格→感じたなどの体験記をまとめておきます。
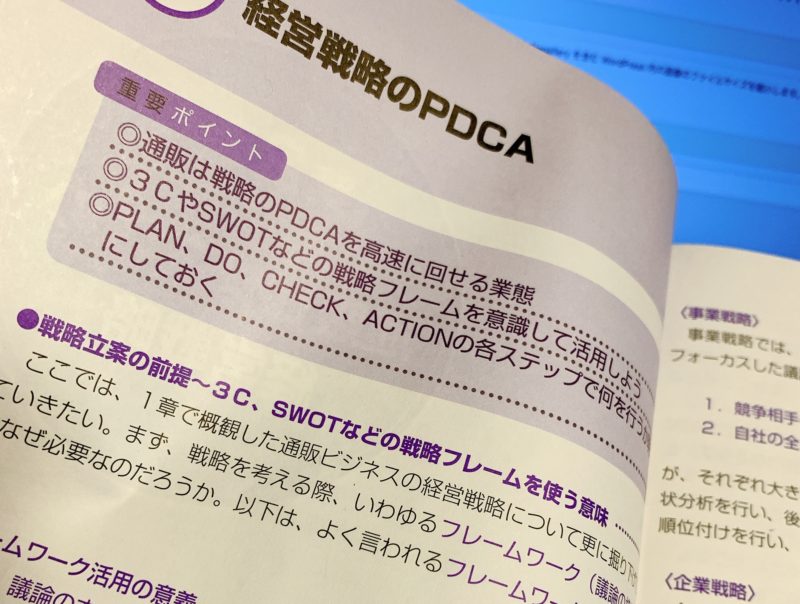
通販エキスパート検定の難易度・合格率は?
公式サイトによると、1級の取得難易度は2016年で66%なんだそう。
なんとなく受験したら合格できない数字…かもしれないですね。
でも真面目に勉強したら、まず間違いなく合格できるはずです。実際に66%という数字ほど、難しい試験だとは思えなかったです。
とはいえ、闇雲に1級から受けるのはどうなんでしょう…。
どの級から受けるべきか?
通販エキスパート検定は3級から受験することができます。
3級は通販の基礎、2級は実務レベル、1級が経営戦略やマネジメント。さらにその上のスペシャリスト資格(カスタマー・セントリシティ、データドリブン・マーケティング)も新設されています。
通販ビジネスに初めて携わる人が1級を受けても、さすがに難しいかもしれません。
実務レベルは、だいたいわかっているつもり。
CPAやLTVなど指標についても、ある程度知っているつもり。
景表法や薬機法なども、なんとなく分かっているつもり。
胸に手をあてて、上記のことが自分に当てはまると感じるならば、あなたはきっと1級でも合格できるレベルだと思います。あくまでも主観だけど…。
そんな場合なら、1級さえ取得すればよいわけでして、3級、2級はスキップしました。
ただ、わかっているつもり…ってなんとなく格好悪いんで、受験前に2級のテキストは読みました。これで理論武装はバッチリかと思います。
通販エキスパート検定1級の合格まで、勉強時間はどのぐらい必要か?
私の場合ですが、1月に決意表明をし、なんだかんだで、1月下旬から公式テキストを買って読み始めました。
2020年の試験がスタートしたのが、4月下旬。
毎年、春と秋に試験が実施されているそうなので、前半の試験をクリアした形になります。
というわけで受験勉強の時間は実質3か月かかりました。
とにかく公式テキストがないと始まりません。これだけはどうしても必要です。
勉強時間の実質は1か月ちょっとかも?
そう考えると長いと思えるかもしれません。ですが、実際は通勤時間に30分ほど、テキストを読んでいただけ。
途中、睡魔に襲われたり、落語を聞いちゃったり、LINEしたり、株価が気になったり。。。ほとんどやってないか。
根を詰めて一気にインプットしないならば、じっくり3か月あれば十分合格レベルに達するでしょう。その間、1か月間は2級のテキストを読んでいたので、厳密にいうと2か月、いや、実質的には1か月ちょっとかもしれません。
ただし、前提条件はあるかと思います。
通販ビジネスの理解がまったくないなら、3級、少なくとも2級のテキストは読んでおくべき。
でも、ざっくり通販ビジネスの概念が理解できていれば、うーんと、たとえば2,3年携わっているようならば、3か月の学習期間で十分なはずです。
もうちょっと時短で合格する方法はあるのか?
えー!1か月ちょっと!?そんなに時間ないんですけどぉ〜、2週間ぐらいで合格できないのぉ〜という、ファンキーなあなた。
スーパーハイな勉強方法、ありまっせ!
テキストの内容を1週間で熟読し、テキストの問題を解きまくる!それが合格への近道です。
問題集なんて要りません(そんなものあるのか知りませんが…)。セミナー受講なんで時間の無駄です。公式テキストの練習問題だけで、十分っす!
なぜなら、実際の検定試験で出題される問題は、
公式テキストの練習問題とほぼ同じだからです。
大事なことなので繰り返します。
難しい問題は、出ませんでした。
仮に、難しい問題が出題されたと感じたのならば、
それはテキストの内容を理解できていない証拠。
おまえが悪い!ってやつです。
少なくとも私が受けた試験では、意地悪な問題は出題されていません。
出題される問題は、少しだけ言い回しを変える程度はありましたが
テキストに載っている問題とほぼ同じです。
つまり、テキストの問題を解きまくって、
解答を覚えてしまえば合格できます。
理解を早めるひと工夫が合格を近づける
テキストは、言い回しが回りくどくて、理解しにくい箇所が多いです。
通販は、中間流通を通さず、顧客からダイレクト・レスポンスが得られる特質を活かして、常に「現状分析〜仮説の構築〜計画立案〜実行〜検証」のサイクルを綿密に回すことができる。
この程度の説明ぐらいなら、さほど難しくありません。
でも、これはどうでしょう。
下の図は本検定の新コース「カスタマーセントリシティー〜顧客中心主義」で紹介しているフレームワークだが、戦略を事業戦略と顧客戦略の2つに分割し、この両者が価値創造プロセスと情報管理プロセスとで相互フィードバックの関係になることに注目してほしい。
正直、私は「は?」…となりました。
こうした説明文を、なんとなく理解したつもりで読み進めていても、途中で、自分を見失います。
ですので、極力余計な文章は、極力読み飛ばす!著者が説明したいことの本質を何かをよーく考え、理解につとめました。
先ほどの説明文でしたら、言いたいことは…
- 戦略を事業戦略と顧客戦略に分割する。
- 価値創造プロセスと情報管理プロセスとで相互フィードバックの関係になる。
- そこに注目せよ!
ってな具合です。
通販エキスパート検定の頻出問題や抑えるべき項目は?
1度しか受験していないから断言はできませんが、公式テキストからまんべんなく出題されていました気がします。
それと通販で活用される指標については正しい理解だけではなく暗記の必要はあるかと感じました。
たとえば3CやSWOTの意味とか。それと、KGIとKPIの違いなども覚えておくべき。
出題される問題はこんな感じ…。
問:3C分析の対象として不適切なものを選べ
1 Customer
2 Competitor
3 Communication
4 Company
これを勘に頼っていたのでは、正解は導き出せません。
答えは、3(Communication)です。
また、ほとんどの問題が「不適切なものを選べ」、もしくは「適切なものを選べ」の選択形式をとっています。記述式ではありません。
「不適切もの」なのか「適切なもの」なのか。
どちらを質問されているかをよく確認してから、答えを導くのがよいです。
他にテキストを読んでいなくとも、常識で正解を導き出せる問題も出題されました。
問:コンプライアンス上、マネジャーが看過してはならい項目として当てはまらないものを選べ。
1 メモリースティックなどでの自宅へのデータ持ち帰り
2 業務手順書の無視
3 サービス残業
4 業務時間外の部下の過ごし方
正解は、4。
常識的に考えれば理解できるような問題ですね。
こうしたサービス問題も、絶対に落としちゃいけないっす。
通販エキスパート検定まとめ
さて、以上をまとめるとこんな感じではないでしょうか?
無事、一発合格できて良かったです。
次は、データドリブンを勉強しておくか。
給料上げてくれないかなぁ。